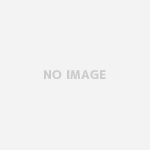学生時代に第三種電気主任技術者の資格を取得していた私が、第二種電気主任技術試験に挑戦するまでと自己採点結果についてまとめました。
このページの内容
第二種電気主任技術とは、一般財団法人電気技術者試験センターによって実施される、経済産業省管轄の電気の資格で、電圧17万ボルト未満までの電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督を行う(発電所や大規模工場、一部大型商業施設などで必要です)ための国家資格です。
電気主任技術は第一種~第三種まであり、扱うことのできる電圧が異なり、第一種が一番上位の資格となります。
第三種、及び第二種と第一種の一次試験は、全4科目を3年以内に取得すればよいのですが、第三種で合格率は約10%(合格者数÷1科目以上受験した人数)、第二種一次は合格率約25%(そもそも全国で受験者数が少なく、例年7000人弱しか受験者がいない)と、そこそこ難易度が高い試験となっています。
令和2年の試験の申し込みは5月26日~6月11日と試験の約3カ月前にあり、申し込みはしてあったのですが、やはり今年は新型コロナウイルスの影響があったため、直前まで受験を見送ろうかどうしようか悩んだのと、個人的な用事がいくつか重なってしまったため、試験対策をスタートするのが遅れてしまい、9月に入ってからとなってしまいました。
スタートが遅くなってしまったため、今回だけですべての科目を合格するのはあきらめ、理論と電力の2科目を集中して勉強することにしました。
勉強方法は、一応参考書を1冊購入し、公開されている過去問をひたすら解くという方法です。
初め3日ほどは、過去問3年分ほどを答えを埋めながら写経しながら、問題を解いていくということを実施しました。
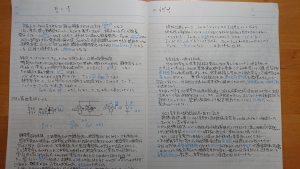
この写経によって、問題の傾向をなんとなく掴むことが出来ました。
その後5日間で、公式サイトに公開されている過去問全11年分を、ひたすら解きながら、分からないところを参考書を見ながら解答を埋めるという方法で問題を解いていくことによって、問題に慣れていきました。
次の2日間は、印刷しておいた過去問(全科目)に、直前に見返すために赤ペンで答えを文書として書き込むという作業に時間を費やしました。
この段階で試験前日になりましたので、あとはひたすら過去問を見直しながら、解き方をおさらいをし、諦めている機械科目と法規科目も目を通して、ざっくりとした記憶を作っておくという方法で一日を使いました。
ここまで、1日当たり約3~4時間、前日のみ丸っと1日を費やすという時間配分で対策を実施しました。
試験当日は朝一時間前くらいに会場に到着するように用意をし(今回はTKP金沢カンファレンスセンターという場所でした)、到着後は一番初めに行われる、理論科目で使われる公式等の復習等に時間を割きました。
1科目目の理論は、途中退出せずに時間を最後まで使い切って回答していきました。
2科目目の電力は、1科目目をギリギリまで解いていたので、復習に使う時間はあまりとれずに突入しましたが、電力科目そのものの傾向としてほとんど計算がないため、退出可能時間前には回答を終えて、退出可能時間になると同時に退出することが出来ました。
昼休みは金沢城公園が近かったので、近くのコンビニで昼食を購入して、ベンチで昼食を取りながら午後からの科目の準備として、答えを書き込んだ過去問を読み込みました。
3科目目の機械と4科目目の法規は、ほとんど準備をしていなかったダメもとの受験でしたので、どちらもあまり時間をかけずに回答を終えました。
電気主任技術試験の解答は週明けに公開されるので、その回答を元に自己採点していきます。
私の自己採点結果は次のようになりました。
理論:64点
電力:64点
機械:40点
法規:52点
合格基準は60点以上ですので、当初の狙い通り理論及び電力はおそらく合格できていると思われます。
残り2科目はまた来年挑戦していきたいと思います。